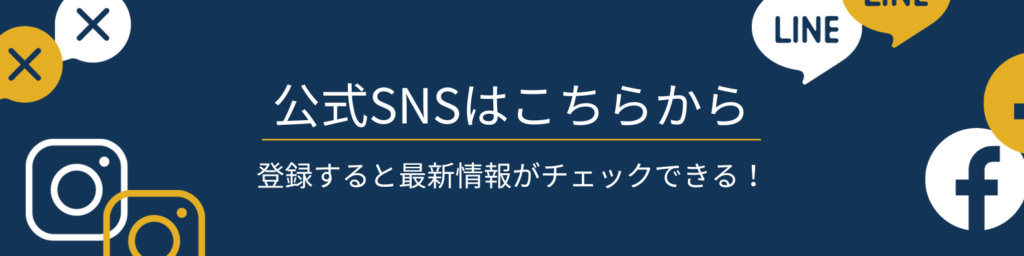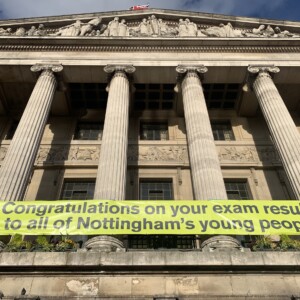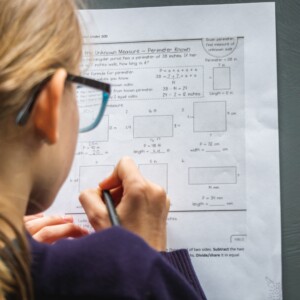【イングランド/ノッティンガム】イギリスから乗り越えた日本の高校受験
皆様、こんにちは。イギリスからRyokoです。
私たち家族は、夫の駐在のためにイギリスで3年半を過ごしました。そして、この春、日本へ帰国します。中学3年生の息子は、イギリスのYear7から現地の学校に通い、Year10の途中で日本へ戻ることになります。
今年の2月には高校受験のために一時帰国し、希望する高校に合格しました。駐在生活には終わりがありますが、息子は「帰国」をどう捉えたのか、また、どのように受験へ向き合ったのかを振り返ります。
帰国への意識 – 日本とのつながり
イギリスでの生活中、息子は2回日本へ一時帰国しました。東京と私の実家がある福岡に滞在し、日本の空気や文化を再認識していたようです。
もともと彼は小学生の頃に東京で中学受験塾に通っていたため、日本の受験に対する感覚はありました。また、YouTubeで日本の情報を頻繁にチェックしており、食べ物系の動画、コント、プロ野球の実況中継などを通じて、日本への興味を持ち続けていました。
一方、イギリスの現地校ではYear10に入ると、クラスメイトたちがGCSE(イギリスの義務教育修了試験)に向けて真剣に取り組み始めました。保護者間のWhatsAppのグループでも、おすすめの家庭教師を紹介し合うなど、イギリス人にとっての一大イベントに向けた意識が高まっている様子がうかがえました。もちろん息子も同様に、GCSEを受ける前提で必須の英語、数学、理科に加えて、スペイン語、ビジネス、地学などの選択科目を選択し、各科目の学習をこなしました。
そんな中、息子に「日本に帰って英語で学ぶ選択肢もあるし、寮に入ってイギリスに残るオプションもあるよ」と時々問いかけました。
最初は「日本よりもリラックスして過ごせそうだからイギリスに残りたい」と言っていましたが、最終的には「日本語で学びたい!」という結論に至りました。小学生のときに取り組んでいた野球ができる環境や、日本語での学習の方が自分にとって自然だという思いが強かったようです。
したがって、目指す学校はインターナショナルコースなどで国際色を強く打ち出した学校ではなく、歴史のある、伝統的な高校を目指して国語、数学、英語の学習をすることにしました。
受験への向き合い方 – 「塾辞めてもいい?」
日本語の学習のため、中学1・2年の間は週末に日本人補習校へ通っていましたが、日本の高校受験を見据えて、中学3年生からはロンドンにある日本の塾にオンラインで参加していました。現地には20名以上の同級生が通っており、さらにフランスやドバイなど、イギリス以外からのオンライン参加者も何名かいました。
中学3年の夏休みには、塾からは「9時9時運動」(朝9時から夜9時まで、2時間の休憩を除いて自主的に10時間勉強すること)が推奨されており、息子も自宅でそれを意識して一日を過ごしました。
しかし、秋頃、息子が「塾の時間を減らして、自分で勉強するスタイルに変えたい」と言い出しました。最初は「この時期に?」と驚きましたが、彼は「自分で復習する箇所を決め、理解できていないところをやり直したい」という明確な理由を持っていました。確かに、私自身も中学・高校時代、先生の話を聞くよりも、自分で教科書を読んでまとめたり振り返ったりすることを好んでいたなと。
結果的に、彼は受験勉強を「自分ごと」として捉え、取り組み方を自身で確立していったのです。
変化のプロセス – チェンジマネジメントの視点から
息子の受験への取り組みを見ていると、私自身が企業で変革リーダーを任された際に、人が変化を受け入れるプロセスとして学んだ、ProsciのADKARモデル(Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement)が連想されます。このモデルに照らし合わせると、息子の受験への向き合い方には、次のような段階があったように思います。
- Awareness(気づき)
- 日本の高校受験の状況や、自分が置かれている環境や立ち位置を理解する。日本の情報から、何もしないことへの危機感を持つ。
- 真剣に取り組まない場合のリスクと、よりよい結果を得たときのメリットを認識する。
- Desire(やりたいと思う)
- 日本での学習環境や、野球を続けることを想像する。
- 受験結果は自分の未来につながるという思いを持つ。
- 自分はできると信じている。
- Knowledge(知識を得る)
- 受験に必要な学力や学習方法の習得についての情報を得る。
- 自分にとって効率的な勉強方法を模索する。
- Ability(実践できる力を身につける)
- 受験直前期に自分なりの学習スタイルを確立する。
- 塾に依存せず、自分が問題を解き、解説を理解する。周りに支援を求める。
- Reinforcement(定着・強化)
- 自分の学力を客観的に理解し、ゴール達成までの行動を計画した経験が、今後の学び方にも影響を与える。
このプロセスはAwareness(気づき)から始まり、その後はDesire, Abilityと順番に通っていくものとされています。そのため、変化をスムーズに乗り越えるのに重要なのは、Awareness(気づく)、Desire(やりたいという気持ち) です。企業の変革でも同様ですが、人間は正論だけでは動きません。自らが気付き、やりたい!と思うように感情を動かすことが必要なのです。観察していると、息子にとっての大きな原動力は、「何もしないことへの危機感」だったのではないかと感じています。
受験を通して得たもの
イギリスでの3年半の生活を経て、日本の高校受験を経験した息子は、単に学力をつけるだけでなく、「受け身ではなく、勉強のプロセスに疑問を持ち、決断し、行動する」ことを実践しました。
受験というのは、単なるテストではなく、自分の未来を考える機会として捉える。家族としては、息子のことを信じ、選択を尊重しながら、ポジティブなフィードバックを心がけました。
現地校に戻り、久しぶりにクラスメートに会った際、「今が一番楽しい!」と言っていました。最初は聞き取ることで精一杯だった英語も、今では会話を続けたり、自分から話題を提供したりすることができるようになったとのこと。充実しているときに、次のステージに移って変化を楽しむのも人生のオプションですね。
人は皆、変化を「自分ごと」にして前向きに乗り越えられます。日本での次のステージも、もうすぐ始まります。

秋吉 良子
Ryoko Akiyoshi
- 居住国 : イングランド
- 居住都市 : ノッティンガム
- 居住年数 : 3年
- 子ども年齢 : 15歳
- 教育環境 : 現地私立中学校